歴史に残る贈り物
- 光武帝の金印
-
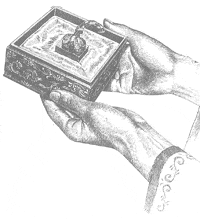
「倭人の礼には漢の礼を尽くして応えよ。」
中国の後漢時代。建武中元元年(西暦56年)、倭奴国王の使者・大夫が初めて漢の首都・洛陽へ到った。
国を発って半年、小船で海を渡り馬に揺られて大陸を進む、長く険しい旅だった。
朝貢のため宮殿を訪れ、通された一室にはすでに他国の使者が控えていた。
「あれは南方諸国の者。持っているのは宝石の包みでしょう」
朝鮮・楽浪郡から付き添ってきた若い将校が大夫に耳打ちした。
確かに、彼らは皇帝に捧げるにふさわしい宝石の数々を持参している。
それに比べて、奴国の貢物はいかにも見劣りがした。
「貢物をここへ。謁見の日取りは追って知らせる。」
漢の小役人の異国悟も、大夫には「どこの蛮族か」とさげすむように聞こえる。
(謁見は許されるだろうか・・・)大夫の心は重たかった。
彼が謁見の日を待つ間、宮殿の奥では廷臣たちが、倭人に与える賜物の件で皇帝に申し出ていた。
「我ら侯公にしか与えられぬ印章を、野卑な倭人に賜る必要がございましょうか」
「それにあの貧弱な貢物」一同はうなずいた。
「ひかえよ」 遮ったのは皇帝である。
「いかに小国とはいえ、奴国王は一国の王。はるばる使者を遣わした奴国の誠を知れ。倭人の礼には漢の礼を尽くして応えよ!」
年老いた光武帝が久々に放った一喝で、賜物は決まった。
年が改まり、建武中元二年正月、大夫はようやく光武帝に謁見を許された。
宮殿から宿に戻った大夫は頬を紅潮させ、小箱を抱えていた。
中に印章が納めてあるという。楽浪の将校が勧めるまま、大夫はふたを開けた。紫の綬(組みひも)をした金印だ。
印面には「漢倭奴国王」と彫ってある。
「これは!」将校は驚きを込めて言った。
「皇帝が贈られる最高の栄誉だ。」
大夫は放心したように黄金の輝きに見入っていた。
光武帝は、はるばる運んだ貢物を快く受け入れられた。
そればかりか、この金印を贈って奴国をひとつの独立国として認められたのだ。
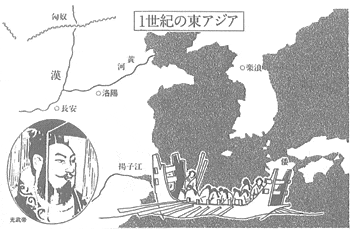 「さ、吉報を一刻も早く奴国へ。」将校の言葉に大夫は力強くうなずいた。
「さ、吉報を一刻も早く奴国へ。」将校の言葉に大夫は力強くうなずいた。
国宝・金印は、昭和54年11月、福岡市美術館の開館を記念して黒田家から福岡市へ贈られた。
大夫が見入った輝きはおよそ二千年の時を超え、市民がともに持つ贈りものとなった。
- 横綱・谷風の庭石
-
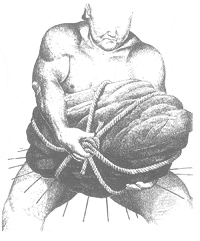
「鞍馬の山から力の限りに運びました。」
天明・寛政期(1780年頃)、無敵の白星街道を突っ走っていた横綱・谷風梶之助は、京都相撲にやってきて、当時の画壇の最高峰・円山応挙と知遇を得た。
「絵では応挙、相撲なら谷風、いずれも日本一」と言われ、ふたりの名声は高いものであった。
ある日のこと、「先生と並んでわしのような者が日本一と称されまするは身に余る光栄。
先生、ぶしつけながらこの谷風のために絵を描いていただけませぬか。
生涯の宝物として子孫にも伝えたく存じます。」と懇望した。
応挙はこの申し出を快諾したが、「金子は無用でございますぞ。」と笑って謝礼の約束はさらりとかわしてしまった。
「はて、どうしたものか?」
谷風は考え込んだまま、応挙と別れた。
それから数日後の朝、応挙はズシーンという物凄い地響きに飛び起きた。
何事かと庭に出てみると、身の丈六尺あまりの巨体に汗を滴らせた谷風が、わが身ほどの巨岩を庭先に置いてニコニコと笑っている。
「これは、いかがなされたのじゃ。」
応挙の驚きに谷風は答えた。
「子孫代々にまで伝える家宝にと、先生の絵を所望いたしました。そのお礼には日本一の贈りものでなければ、と思案はしてみましたが、先生の絵にふさわしい物など何一つ持ってはおりませぬ。わしの取り柄といえばただひとつ、この剛力のみ。さすれば、せめてこの剛力でと思い当たりまして・・・。ここ二、三日、お庭にふさわしい石を捜して鞍馬の山を駆け巡りました。そしてやっと見つけましたのがこの岩。谷風、渾身の力をふりしぼってお庭まで運んでまいりました。さ、先生、どこに配しましょうか?」
谷風の心づくし、力づくしの謝礼は、応挙の胸にズシンとくるものがあった。
「お志、ありがたく頂戴いたします。このうえは応挙、会心の絵を描いてさしあげましょう。」
この重たい贈りものに感銘を受けた応挙は、約束の絵を一年以上の歳月を費やして見事に完成させた。その間、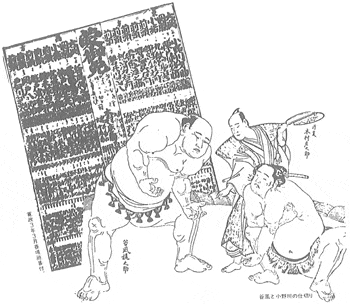 満足せずに反故にした作品は100枚を超えていたという。
満足せずに反故にした作品は100枚を超えていたという。
応挙にしか描けぬ絵には、谷風にしかできぬ贈りもので報いたい―巨岩に込めた谷風のひたむきな思いは、応挙の心に末永く残ったに違いない。
だからこそ人々も「あっぱれ、日本一の贈りもの」と語り伝えていったのであろう。
- 黄金の杖
-

「我々は、いつまでもあなたの杖です。」
1883年、ジョゼフ・ピュリッツァーは16年住み慣れたセントルイスを去る意思を固めた。
彼の新聞、「ポスト・ディスパッチ」紙の編集長が起こした事件の責任を問われ、35歳の若い社主が初めて味わう苦渋だった。社員はそろって彼の辞意に反対した。
「残念だがこれしかないんだ。私はニューヨークで出直すよ。」
ピュリッツァーはそういうものの、社員たちは最高の社主を失うのが残念でたまらなかった。
4年前、彼がこの新聞を買い取った頃、社員には活気も誇りも感じられなかった。
発行部数はわずか2000。地元のニュースは他紙から失敬するありさまを見て、若い社主は第一線に立って記事を書き、紙面に活を入れた。
活気づいた同紙は急速に読者を増やし、今ではセントルイスで最も有力な新聞にまでなっていたのだ。
幹部社員の説得にもかかわらず、ピュリッツァーの決意が変わらぬことを知ると、若い社員の間から別の意見が出た。
「ディスパッチ紙は、我々の手で守ろう。ボスにはニューヨークで活躍してもらうんだ。」
そして全社員の気持ちを伝える贈りものをすることが決まった。
セントルイスを去る日、ピュリッツァーは社員の前で別れを告げた。
そのとき、社員の一人が進み出て、用意した贈りものをおもむろにさし出した。
杖である。頭に黄金の握りがついた特製の品だ。
「私たちの変わらない感謝と尊敬のしるしです。我々はいつまでもあなたの杖です。ニューヨークでもいい仕事を。」
ピュリッツァーは一瞬、言葉を失った。
杖を握りしめる彼に、社員の熱い視線が集まる。
どの目も、負けないでくれ、もっと大きな目標を目指せと語っている。
「ありがとう。」若い社主はそれだけ言うのがやっとだった。
この年、ニューヨークに出たピュリッツァーは、赤字続きの「ワールド」紙を買い取り、有力紙がしのぎを削る新聞界に目覚ましい攻勢をかけた。
 そしてセントルイスの期待に応えるように、「ワールド」はついに全米一の新聞に育って言ったのだ。
そしてセントルイスの期待に応えるように、「ワールド」はついに全米一の新聞に育って言ったのだ。
ニューヨークでの激しい戦いの中で、この黄金の杖はいつも彼を勇気づけ、励ましてくれたに違いない。
彼の遺志で設けられた「ピュリッツァー賞」は、彼に続くジャーナリストに贈られる“ピュリッツァーの杖”である。
- 久次郎のマンドリン
-

「お前にしかできん曲ば作ってくれ!」
大正8年(1919年)5月。朝鮮京城で善隣商業高校へ通う政男少年のもとに、一個の小包が届いた。
贈り主は、大阪で金物屋を営んでいるすぐ上の兄・久次郎だ。
8年前、父が亡くなり、故郷の田口村(現在の福岡県大川市)から一家を挙げて朝鮮に渡ってきて以来、政男には辛いことばかりであった。
叩き上げで金物屋の主人となった長兄は、政男の中学進学の夢を「どうせ商人になるんやけん」と相手にしてくれなかった。
まして、彼の胸中に燃えさかる音楽への情熱や天分などを、理解してもらえるわけがない。
最愛の母までが「お前は誰に似たんやろうねぇ」とため息をつくのだった。
そうした中で四番目の兄・久次郎は、政男を何かにつけてかばい、特異な才能を認めてくれた。
小包を手にすると、兄への懐かしさがこみあげ、急いで包みをほどいた。
その瞬間、政男はまるで雷に打たれたような気がした。以前から欲しくてたまらなかったマンドリンではないか!夢中で抱きしめ、そっと弾いてみると甘く切ない音色が響いた。
その音を聞きながら、政男ははっきりとマンドリンに託した兄の心を感じていた。
「政男!音楽ばするごたっとやろ。するとよか。せめてお前だけは、自分の才能ば思う存分活かす道に行くがよか。このマンドリンで、お前しかできん曲ば作ってくれ!」
政男は泣いた。高価な楽器を手にすることができた喜びよりも、家のために三人の兄たちに続いて黙々と商人の道を歩いている兄が、せめて弟にだけは・・・とかけてくれた精いっぱいの思いやりと愛情が心にしみた。
この兄にもきっと進みたかった道が、思うままに築き上げたい人生があっただろうに・・・。
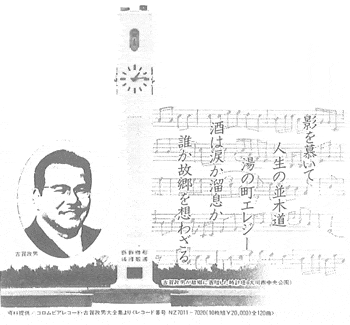 この時の古賀政男とマンドリンの出会いが、4年後には「明大マンドリン倶楽部」の創設に、そしてやがては日本人の心を唄う数々の古賀メロディの誕生へとつながっていったのである。
この時の古賀政男とマンドリンの出会いが、4年後には「明大マンドリン倶楽部」の創設に、そしてやがては日本人の心を唄う数々の古賀メロディの誕生へとつながっていったのである。
兄・久次郎が贈ったマンドリンには、自分の人生に対する哀しみと、弟のそれに向ける深い愛と期待が託されていたのだろう。
だからこそ、この贈りものが弟・政男の人生を拓き、音楽家への道に確かな意図筋の光明を灯すこともできたのではないだろうか。
- イザベラ女王の帆船
-
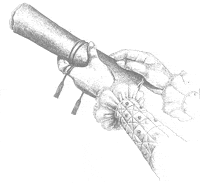
「私は、そなたの熱意に賭けてみたい。」
1486年、コロンブスは初めてスペイン女王イザベラ一世に謁見を許された。女王に西廻りインド航路の計画を述べるためである。「地球は丸い」というだけで異端扱いされた当時、それを実証しようというのだ。
彼は、航海に必要な資金の援助を諸国の大商人や国王に求めたが、誰も相手にしてくれなかった。思い余ったコロンブスは、聡明で名高いイザベラ女王に願い出たのだ。彼は女王の前に進み出て、計画の全てを語った。
「どうぞ三隻の船を私にお与えください。お国の名誉と富のために。」
廷臣たちの嘲笑があたりを包んだ。しかし、女王は答えた。
「よろしい。そなたの計画を吟味させましょう。」
女王の言葉にコロンブスは明るい希望を持った。
しかし、地理や財政の専門家からなる「審議委員会」が結論を出すまで、コロンブスは4年間も待たねばならなかった。だが、やっと出た結論は「否決」であった。
諦めきれないコロンブスは、もう一度審議を願い出たが、1カ月もたたぬうちに再び否決された。
1492年1月、委員会は女王の前でコロンブスにその旨を通告した。(もうダメだ・・・)すべては終わったと思い、失意の数日間を過ごしたコロンブスは、行くあてもなく都を去ろうとしていた。
そこへ女王からの使いが訪れた。
「急ぎ戻ってほしい」との伝言である。おそるおそる入った謁見室には女王が待っていた。
「私は三隻の船とともに、そなたをインドに派遣することにしました。そなたの熱意にかけてみたい。必要なものはすでに命じてあります。」
あまりの驚きのために、コロンブスは息も詰まる思いだった。コロンブスはその場にひざまづき、深々と頭をたれた。
1492年8月3日早朝、コロンブスの率いる艦隊は、未知の新世界に向けて出港した。
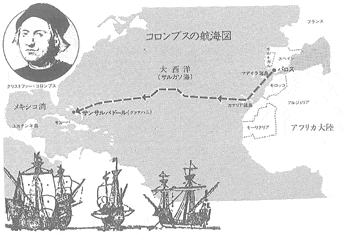 権勢を誇ったイザベラにとって、三隻の船を用意することはそれほど困難であったとは思いない。
権勢を誇ったイザベラにとって、三隻の船を用意することはそれほど困難であったとは思いない。
むしろ、廷臣や国民の嘲笑の中でコロンブスを信頼することの方が、ずっと難しいことだったろう。
苦難の続く航海の中で、コロンブスを力づけたものは贈りものに込められた信頼の重みだったであろう。


