歴史に残る贈り物
- H・フォードのT型車
-
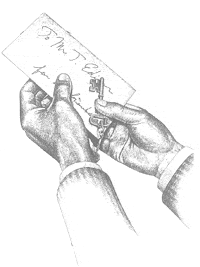
「第一号車のオーナーは、あなたになって欲しい。」
1913年秋。ヘンリー・フォードは親友エジソンを別荘に招いた。発明王エジソンはこのとき66歳。
フォードより16歳も年長だが、ふたりの親交はフォードがかつて「エジソン電気会社」の技師だった頃から続いている。
ふたりはいつものように近くの川で釣り糸を垂れていたが、今日のフォードは何か思い悩んでいる様子だ。
エジソンは話しかけた。
「最近、こんな話を聞いたけど知っているかい?」
エジソンが聞いたのは、フォード車を中傷する噂である。
たとえば、フォード車はネジが外れやすいので、後部に磁石をつけて走るとか、安いから1年でダメになる・・・などだ。
どれもが業界の中傷や妬みから出ている誤解である。
フォードの苦笑を見て、エジソンは続けた。
「でも心配は無用さ。本当は誰もが君の車に乗りたがっている。もっと誰もが買えるように安く、たくさん作ることだ。そうすれば噂なんかひとりでに消えてしまうさ。」
フォードはしばらく釣り糸を見ていた。
そして力強く答えた。
「ありがとう、決心がついたよ。」
翌1914年、産業界の正月はフォード社の値下げ宣言で明けた。
他社の自動車の半額に近い490ドルで、新しいT型車は売り出された。それはフォードが考えていた「流れ作業による自動車生産方式」により初めて可能になったのだ。
エジソンの助言は当たった。
当時、自動車は金持ちの贅沢品と見られていたが、T型車は数々の改良を加え、コストを下げて贅沢品の自動車を気軽な人々の足に変えていったのだ。
フォード社の発表でアメリカ中が湧いていた頃、エジソン邸に1台のT型車が着いた。
運転手によると、フォード社長からエジソンへの贈りものだという。
半信半疑のエジソンは車のカギを渡されて、半年前の一件を思い出した。
フォードからの手紙も添えられている。
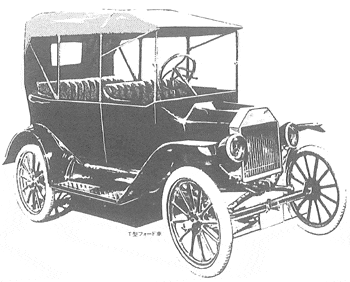 「新しいシステムによる第一号車です。同型車はいずれ国中にあふれるでしょうが、記念すべき最初のオーナーは、ぜひあなたになってほしい!」
「新しいシステムによる第一号車です。同型車はいずれ国中にあふれるでしょうが、記念すべき最初のオーナーは、ぜひあなたになってほしい!」
エジソンはシートに座るとハンドルの感触を確かめ、おもむろに鍵をさしこんだ。
フォードの感謝の心を伝える爽やかなエンジン音が庭先に響いた。
- 伊藤博文の通学鞄
-

西洋では、ランセルと申しております。
明治20年(1887年)、明治天皇の第三皇子(のちの大正天皇)がいよいよ学習院ご降学と決まった。
ご誕生以来病弱であった皇子がつつがなく成長され、この度のご通学となったのだ。
父君天皇はもちろん、総理大臣・伊藤博文や皇子のご養育に当たっていた人々の喜びは大きかった。
ご通学の報を受けたとき、伊藤博文は皇子に特製のご通学祝いをしようと思い立った。
お祝いの品を依頼してのち、伊藤は出来上がりが待ち遠しくて仕方がなかった。
その日、伊藤は青山御所へ急いだ。外はすでに夜である。
「宮様は?」養育主任の老臣を見るなり尋ねたが、もうおやすみとのことである。
伊藤は今まで張りつめていたものが一気にぬける思いがした。
「首相、こんなお時間に何事で?」老臣は問い返した。
「実は、宮様のこのたびのご通学に当たって、お祝いの品を持って参ったのだが・・・。」
伊藤は包みを開けてみせた。老臣が見たのはベルトが2本ついた鞄である。
「これは?歩兵が背負う背嚢のようですが・・・。」
老臣は伊藤の意を察しかねたようだ。「これを宮様に?」
「いかにも。先年、欧州へ行った折見聞したもので、西洋ではランセルと申して学童が通学に使っております。」
(また西洋か!)老臣は伊藤の西洋好みを内心苦々しく思っていた。
しかも皇子への献上物に歩兵が使う物とは心外である。
しかし、老臣の気持ちなど意に介さない様子で、伊藤は続けた。
「宮様のご通学にこれほど最適なものはありますまい。中に学用品をいれて背負われれば、お身体も楽です。さらに咄嗟の折にも両手があいておるので安心というものです。」
(なるほど。) 老臣はやっとランセルにこめた伊藤の真意を汲みとった。
翌日、ランセルは皇子の手元に届けられた。
数多く寄せられた贈りもののうちでも、ランセルはことのほか皇子を喜ばせたという。
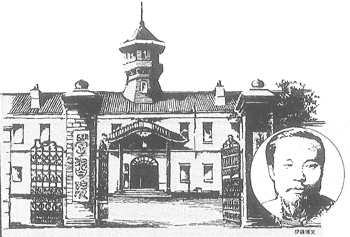 その後、ランセルは学習院で正式に採用されるにおよび、学童の通学鞄として全国に普及していった。
その後、ランセルは学習院で正式に採用されるにおよび、学童の通学鞄として全国に普及していった。
現在の「ランドセル」は、ランセルが訛ったものである。
相手の身になって選ばれた贈りものこそ、最高の贈りものといえる。
伊藤のランセルは、物珍しさよりも通学の身を案じるまごころの所産ではなかっただろうか。
- 坂本龍馬の月琴
-

「わが身と思うて、膝に抱かれたく…」
幕末維新の風雲児坂本龍馬の恋人は、数人伝えられている。
その中からひとり、妻の座に選ばれたのは京の女性おりょうである。元治元年(1864年)、龍馬は始めて長崎を訪れた。
異国の香りがするこの町をすっかり気に入り、連日のように歩き回るうち、龍馬は聞き慣れない音曲を耳にした。
異国の楽器らしい。
舶来物を扱う唐物屋に飛び込んで尋ねると、やはり見慣れぬ楽器を取りだしてきた。月琴という清国伝来の弦楽器である。
弦をはじくと、琵琶に似ているがやや高く、甘い音色がする。
若い女の京ことばを聞くようだ。「面白そうじゃな。」
龍馬はさっそくこの異国の楽器を買い求めた。
京を発って半年後、龍馬は長旅を終え、おりょうのもとへ帰ってきた。
おりょうは胸にたまった寂しさを一気に語りつくそうとした。
しかし、「またすぐ出かける。」という龍馬のひと言に遮られてしまった。
いつもの通りだ。龍馬は急に思い出したように言った。
「そうじゃ、長崎で面白いもんをみつけた!」
「おや、何どすやろ。」
腹立たしい気持ちをぶつけるようにおりょうはおどけてみせたが、龍馬は意に介さない。
「勝手口に置いてあるきに。」
おりょうは小走りに勝手口へ立った。確かに、長さ二尺もある包みが板の間に立てかけてある。
開けると見慣れぬ楽器が出てきた。龍馬が長崎で買い求めた月琴である。そして、走り書きの手紙が添えてあった。「わが身と思うて、膝に抱かれたく・・・。」
飛び跳ねるような文字から龍馬の笑顔が見えてくるようだ。
(あの人は、私の心がわかっている・・・)
おりょうは、不意に切なさがこみ上げてきて急いで部屋に戻ると、龍馬の姿はもうなかった。
月琴は、おりょうが龍馬からもらった初めての贈りものだった。
そしてこの贈りものにおりょうは二人を結ぶ絆を見る思いがした。
のちに、龍馬はおりょうに語っている。「仕事が済めば山中で気楽に暮らすきに、それまでに稽古しちょれ。」
しかし、龍馬はおりょうの奏でる月琴を聞くこともなく、慶応三年(1867年)11月15日、暗殺者の凶刃に倒れた。
不運の時代を生きた龍馬とおりょう、離ればなれに暮らすことの多かったふたりにとって、この贈りものが一本の線となり、心と心をつないでいたのだろう。
- 自由の女神
-

NY市民よ、女神は我々の手で迎えよう!
ニューヨークのハドソン川をさかのぼる船は、まず自由の女神に迎えられる。
右手にたいまつ、左手に独立宣言書、足首には自由を目指して断ち切られた鎖を見せる女神像は、合衆国独立承認100年を祝って、フランス国民から米国民へ贈られた。この計画が生まれたのは1866年、ベルサイユ宮殿の晩餐会に集まった政治家、芸術家たちの間からである。米国独立戦争で勝利を勝ち取った米国とフランスの友情と栄光を、永く両国民に伝えようというのである。しかしこの計画に疑問を投げかけた客も少なくなかった。
それから9年後、この計画はフランスの大衆の手で甦った。基金募集のため「フランス・アメリカ・ユニオン」が組織され、人々は募金の呼び掛けに応えた。像の内部構造の設計は、のちにエッフェル塔を設計したA・エッフェルがあたり、デザインは人気彫刻家F・バルトルディが申し出た。1884年、女神像は完成した。同じ年、パリで盛大な贈呈式も行なわれた。ところが、合衆国では困った事態が起きていた。像を据える台座が、資金不足のために未完成なのだ。大西洋を渡る日を待つ女神に救いの手をさしのべたのは、ニューヨークの市民である。
大衆紙「ニューヨーク・ワールド」は読者に呼びかけた。「女神の製作には、フランスの大衆が募金に参加してくれた。我々も、この誠意に応えようではないか。億万長者の寄付を待つのはやめよう。女神は我々の手で迎えよう!」12万人もの人々がこの訴えに賛同し、5セントから多くても250ドルを基金に寄せてきた。目標の10万ドルはわずか半年で集まり、台座は完成した。全高46メートルの女神像は、214個のケースに分解され、船で大西洋を渡った。除幕式の日、ハドソン川河口の両岸は群衆で埋まった。三食の幕が除かれると、待ち構えていた市民の間から大歓声が湧きあがった。1886年10月28日のことである。
 フランス国民と米国民の信頼と相互理解にこの贈り物が果たした役割は大きい。国から国への贈りもの、それはときには政治、外交以上に心と心を近づけてくれるものなのだろう。
フランス国民と米国民の信頼と相互理解にこの贈り物が果たした役割は大きい。国から国への贈りもの、それはときには政治、外交以上に心と心を近づけてくれるものなのだろう。
- チャップリンの腕輪
-

さっきの店でちょっと失敬したんだ。
1944年のこと。ビバリーヒルズの宝石店にチャップリン夫妻が入ってきた。
54歳のチャップリンと18歳の新妻ウーナ、まるで親子のようなふたりである。この日はウーナ夫人の化粧箱を修理するため、近くの店に出かけたのだ。待っている間、ふたりはショーケースの品々を物色していた。中でもウーナがため息を漏らしたのは、ダイヤモンドとルビーをちりばめたみごとな腕輪だった。
チャップリンも気に入ってしきりに勧めたが、ウーナは自分には高価すぎるといって断ってしまった。彼女はチャップリン夫人になったその日から、つつましい妻に専念することを固く決心していた。チャップリンと36歳も離れた4番目の妻ウーナ、その結婚は当時、ジャーナリストたちの注目の的であった。財産目当ての結婚などという陰口も聞かれた。そのためか、ひそやかな結婚式から半年後の今も 彼女は結婚指輪さえ受け取ろうとしないのだ。
店を出て車に戻るなり、チャップリンは硬い声で言った。
「急いでくれ、フルスピードだ!」車が走り出すと、彼はポケットからそっと腕輪を取りだした。
彼女が先ほどため息を漏らした例の腕輪である。
「君が他のを見ているすきに、さっきの店でちょっと失敬したんだ。」
ウーナは真っ青になった。
「いけないわ!ひどいことを・・・」彼女は車を裏通りに入れ、急停車させた。
「どうしたらいいか、考えてみましょう」「しかし、いまさら返すなんてとても・・・。僕を刑務所に入れたいのかね?」そう言ったものの、ウーナの困りきった表情を見て、もうこれ以上嘘を続けるわけにはいかなかった。
「冗談だよ!」ふき出しながら、彼はウーナに白状した。実は、彼女が他の品を見ている間に、店の奥でそっと買っておいたのだ。
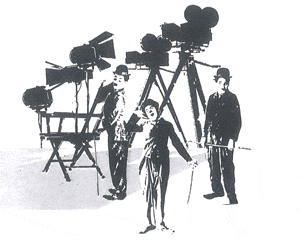 「奥様、腕輪をどうぞ。これでもまだご不満ですか?」少年のようにいたずらっぽい笑顔から、ウーナはチャップリンのまごころを見てとった。
「奥様、腕輪をどうぞ。これでもまだご不満ですか?」少年のようにいたずらっぽい笑顔から、ウーナはチャップリンのまごころを見てとった。
彼女は、いたずらっ子をたしなめる母親のようにあったかい口づけを彼に贈った。
喜劇王チャップリンが、最愛の妻にプレゼントしたこの腕輪は、迫真の演技とユーモアのリボンをかけた愛の贈りものであった。


