西郷隆盛のかんざし
-

「おはんの長か黒髪忘れちゃおりもさんど」
安政六年(1859年)十一月、奄美大島竜郷に配流の身であった西郷隆盛は、美しい島の娘・愛加那(あいかな)と結ばれた。
当時の藩の掟では、あくまでも滞島期間のみに許された夫婦関係である。その不憫さを胸に西郷はこの妻をいとおしみ、愛加那もまた、やがて来る別離を密かに覚悟しつつ、夫の髪をときながら、櫛に残る毛髪を大切に集めたという。
やがて、長男菊次郎が生まれ、結婚二周年を機にやっと構えた新居に移ったその翌日、一隻の飛脚船が、西郷召還の命を伝えたのである。それから十年の歳月が流れた。
維新の大業を成し遂げた西郷は、菊次郎を呼び寄せ鹿児島の英語学校に通わせる一方、いつかは妻に会いに行こうと考えていた。だが、激動する時勢はそれを許さなかった。
明治二年、年の瀬も押し迫ったある日、西郷は自室に菊次郎を呼び寄せた。
いよいよ年が明ければ、岩倉勅使一行に従って上京の途につく決心をしていたのだ。
これが最後になるかもしれない。西郷にはそんな予感があった。愛加那の面影をとそめる菊次郎の顔をまじまじと凝視しながら、西郷は懐から銀製の見事なかんざしを取りだした。
「これを、おまんさあの母御に」菊次郎はよく意味が呑み込めない。
「あの南ん島で過ごした歳月だけが、おいどんにとって人間らしか毎日でごわした。母御に、おはんの長か黒髪はいつも忘れちゃおりもさん、と伝えてたもんせ」
ひとたび上京してしまえば、これから先の自分に私人たる時間は許されない。
愛加那との再会など望むべくもないという思いが彼を駆り立て、在島中はついぞ買い与えることのできなかったかんざしを贈らせたのであろう。
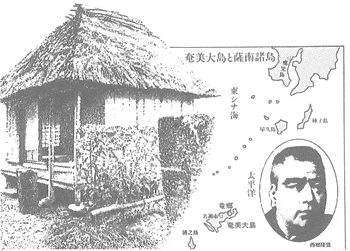 菊次郎は長じて二代目京都市長に就き、その母は一度も島を離れることなく、明治三十五年、ひっそりと66歳の生涯を閉じた。臨終の床にあって、彼女の髪には銀のかんざしが光っていたと伝えられる。私心なきがゆえに回天の偉業を成した英雄、西郷隆盛にも、人として一介の男子としての私情はあった。
菊次郎は長じて二代目京都市長に就き、その母は一度も島を離れることなく、明治三十五年、ひっそりと66歳の生涯を閉じた。臨終の床にあって、彼女の髪には銀のかんざしが光っていたと伝えられる。私心なきがゆえに回天の偉業を成した英雄、西郷隆盛にも、人として一介の男子としての私情はあった。
その象徴ともいうべき銀のかんざしは「歴史の寡婦」となった愛加那をどれほど慰め、励ましたことだろう。


