歴史に残る贈り物
- エルビス・プレスリーのレコード
-
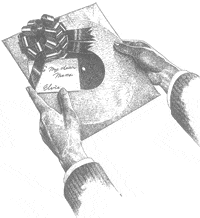
「いつだって僕は大好きなママと一緒さ。」
1953年6月。テネシー州メンフィスのハイスクールを卒業して電気会社に就職したエルビス・プレスリーは、希望にふくらむ胸の片隅で憂鬱な想いも募らせていた。大好きなママに元気がないのだ。一人息子エルビスを母は溺愛した。そして一人息子の歌は彼女の密かな誇りだった。
幼い頃、彼は五千人の観衆が集まるコンテストで1等になった。ハイスクールでは、全校生徒と父母が見守るショーでグランプリに輝いた。母は涙を流さんばかりに喜び、苦しい家計の中からギターを買ってくれたり、心づくしのご馳走でパーティーを開いてくれたのだ。
その母に元気がないのは、長い間の無理がたたって健康を害したことと、一人息子が仕事で忙しくなって家にいる時間がめっきり少なくなったからだった。
人一倍親思いのエルビスに、さびしげな母の姿はこたえた。
「なんとかしなくちゃ」と思っていたある日、彼は町の小さなレコード会社の広告に目をとめ、「これだ!」と叫んだ。
“あなたのレコードを作ってみませんか?両面2曲で4ドルです”
数日後、帰宅したエルビスは「ママ、世界一素敵な歌をプレゼントするよ」と母を蓄音器の前に座らせ、一枚のレコードをかけた。曲は、母の大好きな「マイハピネス」、歌声はエルビスだった。
母は信じられないといった表情から、目に涙をいっぱいためて言った。
「おまえ、とうとう本物の歌手になるのかい?」喜びを押し隠した母の冗談に、エルビスはちょっと照れながら言った。「ねぇ、元気を出して。いつだって僕は大好きなママと一緒さ」
その夜からプレスリー家の小さな窓からは、息子が歌う「マイハピネス」と「心がうずく時」のバラードが繰り返し聞こえたという。
 孝行息子が4ドルで昼休みに吹き込んだ一枚のレコードは、業界人、専門家の耳に鮮烈な印象を残し、やがてロックンロールの王様プレスリーの誕生につながっていった。
孝行息子が4ドルで昼休みに吹き込んだ一枚のレコードは、業界人、専門家の耳に鮮烈な印象を残し、やがてロックンロールの王様プレスリーの誕生につながっていった。
ポピュラーシングル盤の販売世界一にもその名を刻んだプレスリーだが、彼の母にとってはエルビスが贈った最初の1枚こそ、世界で最高のレコードだったはずである。
- 名槍「日本号」
-

「日本一に呑み取られるなら、こいつも本望。」
文禄五年(1596年)正月。京都伏見城下の福島正則の屋敷に、隣家・黒田長政の名代が新年の祝賀に訪れた。
黒田家第一の槍使い母里太兵衛(もりたへえ)である。
正則も太閤秀吉の直臣では、加藤清正に劣らぬ槍を使う。
太兵衛の槍は、そんな正則でさえ一目置き、かつて自藩の槍術指南役にぜひ迎えたいと思わせたほどであった。
一通りの祝賀が済むと、正則は客を酒席に通した。
太兵衛が最初に目を奪われたのは、正則の座の後にかかる槍である。槍身二尺六寸、青貝の螺鈿(らでん)をちりばめた柄を加えると七尺五寸もあろう。
正則が秀吉から賜ったという秘蔵の名槍「日本号」である。
「なるほど、お見事」太兵衛の言葉を待っていたように、正則は話し始めた。
「見事といえば、そちは稀にみる酒豪とか。本日はその腕前を見せてくれぬか?」
返事も聞かず、径一尺余の大盃になみなみと酒を注がせ、
「この一杯、一息に飲み干せば、望みのものを取らせよう。いかがじゃ?」と続けた。
太兵衛は困惑した。名代の身に不覚があってはならぬ。が、正則に引く気配はない。
「恐れながら、あの日本号を賜りますなら」酒席は驚きのあまり静まり返った。
それでも正則に動じる風はない。
「然らば」意を決した太兵衛は大盃の酒を見据えると、一気に飲み干してしまった。
困惑と狼狽が一座を走った。「天晴れじゃ、太兵衛!」沈黙を破ったのは正則である。
やにわに立ち上がると日本号をわしづかみにし、あわてて制する家臣を抑えて言った。
「余の無礼を許せ、これはお手並みに捧げる引き出物じゃ、持って行かれい。日本一に呑みとられるなら、こいつも本望じゃ、ワッハハハハ・・・・。」
このときになって太兵衛はハッと気がついた。
これは正則の精一杯の狂言なのだ。秀吉の手前をはばかり、彼は酒席の戯言にのせて名槍を呑みとらせてくれたのだ。酒の上の余興でなら、秀吉も咎め立てはするまい・・・。
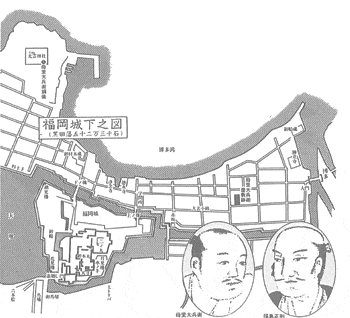 「お心、ありがたく拝領」太兵衛が目の周りを熱く感じたのは、酒のせいだけではなかっただろう。
「お心、ありがたく拝領」太兵衛が目の周りを熱く感じたのは、酒のせいだけではなかっただろう。
「黒田節」には名槍を呑みとる黒田武士の豪快な姿がある。
日本一の名槍を日本一の使い手に贈った正則の機知と豪気もその姿に重なるのである。
- 西郷隆盛のかんざし
-

「おはんの長か黒髪忘れちゃおりもさんど」
安政六年(1859年)十一月、奄美大島竜郷に配流の身であった西郷隆盛は、美しい島の娘・愛加那(あいかな)と結ばれた。
当時の藩の掟では、あくまでも滞島期間のみに許された夫婦関係である。その不憫さを胸に西郷はこの妻をいとおしみ、愛加那もまた、やがて来る別離を密かに覚悟しつつ、夫の髪をときながら、櫛に残る毛髪を大切に集めたという。
やがて、長男菊次郎が生まれ、結婚二周年を機にやっと構えた新居に移ったその翌日、一隻の飛脚船が、西郷召還の命を伝えたのである。それから十年の歳月が流れた。
維新の大業を成し遂げた西郷は、菊次郎を呼び寄せ鹿児島の英語学校に通わせる一方、いつかは妻に会いに行こうと考えていた。だが、激動する時勢はそれを許さなかった。
明治二年、年の瀬も押し迫ったある日、西郷は自室に菊次郎を呼び寄せた。
いよいよ年が明ければ、岩倉勅使一行に従って上京の途につく決心をしていたのだ。
これが最後になるかもしれない。西郷にはそんな予感があった。愛加那の面影をとそめる菊次郎の顔をまじまじと凝視しながら、西郷は懐から銀製の見事なかんざしを取りだした。
「これを、おまんさあの母御に」菊次郎はよく意味が呑み込めない。
「あの南ん島で過ごした歳月だけが、おいどんにとって人間らしか毎日でごわした。母御に、おはんの長か黒髪はいつも忘れちゃおりもさん、と伝えてたもんせ」
ひとたび上京してしまえば、これから先の自分に私人たる時間は許されない。
愛加那との再会など望むべくもないという思いが彼を駆り立て、在島中はついぞ買い与えることのできなかったかんざしを贈らせたのであろう。
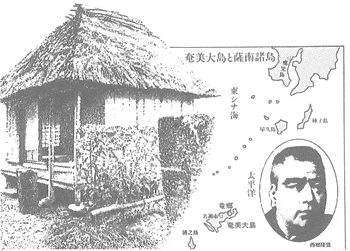 菊次郎は長じて二代目京都市長に就き、その母は一度も島を離れることなく、明治三十五年、ひっそりと66歳の生涯を閉じた。臨終の床にあって、彼女の髪には銀のかんざしが光っていたと伝えられる。私心なきがゆえに回天の偉業を成した英雄、西郷隆盛にも、人として一介の男子としての私情はあった。
菊次郎は長じて二代目京都市長に就き、その母は一度も島を離れることなく、明治三十五年、ひっそりと66歳の生涯を閉じた。臨終の床にあって、彼女の髪には銀のかんざしが光っていたと伝えられる。私心なきがゆえに回天の偉業を成した英雄、西郷隆盛にも、人として一介の男子としての私情はあった。
その象徴ともいうべき銀のかんざしは「歴史の寡婦」となった愛加那をどれほど慰め、励ましたことだろう。
- シーボルトの医療器具
-
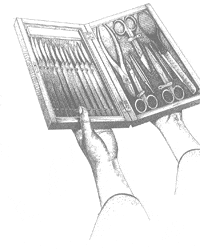
「育ちかけた医学の芽を枯らせてはならない。」
文政十一年(1829年)十月、後にいうシーボルト事件が起きた。長崎オランダ商館の医師シーボルトが禁制の日本地図を所有しているのが発覚、そのために日本追放の裁きが下されたのだ。
シーボルトには、日本女性お滝との間に2歳半になる娘イネがいた。頑迷に鎖国を守るこの国に妻子を残して去るのは、もはや生涯の別れに等しい。シーボルトは思い悩んだ末、二人のことを私塾の門人に託すことにした。
文政十二年十二月五日早朝、シーボルトを乗せたオランダ船が出島の岸壁をひっそりと離れた。
お滝たちの姿はなかった。罪人の見送りはもとより許されない。
しかし、汽船が小瀬戸にさしかかると小船が朝霧のなかから姿を現わした。
約束通り、お滝がイネを抱いている。
門人が密かに漕ぎ寄せた船に飛び乗り、シーボルトも小瀬戸に向かった。
二艘の船が浅瀬に並ぶ。シーボルトは小さな木箱をお滝の前にさし出した。
「これをおイネに」お滝はにわかに理解できない様子だった。
愛用のメスやハサミ類を収めたこの箱は、今まで誰にも触れさせようとしなかったものだ。
「大切な道具を、なぜおイネに?」シーボルトは娘を抱き寄せながら答えた。
「この子に継がせて、立派に育ててほしい。やっと育ちかけた医学の芽をこのまま枯らせてはならない」その時、船がぐらりと揺れた。潮が満ちてきたのだ。急き立てられるように、シーボルトの船は小瀬戸を離れた。この日からイネのつらい運命が始まる。
激動する歴史の中で彼女は父の志を継ぎ、門人たちから外科医の手ほどきを受け始めた。
そして婦人科の修業を終えたのは27歳の秋。安政元年(1854年)、日本最初の女医が誕生したのである。あの日から数えて30年後、イネは父との再会を果たした。
懐かしそうに見つめる父シーボルトに、イネは古びた木箱をさし出した。
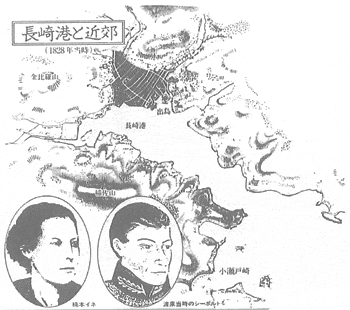 「覚えておいでですか?」ふたを開けると医療用の器具がキラリと光った。「これを今も?」父の驚きに、イネは嬉しそうに答えた。「はい。これが私の父だったんですもの」
「覚えておいでですか?」ふたを開けると医療用の器具がキラリと光った。「これを今も?」父の驚きに、イネは嬉しそうに答えた。「はい。これが私の父だったんですもの」
日本に近代医学の根を植えつけ大きく育てた陰に、ドイツ人の父から娘に贈られた古びた医療器具があった。
「医は仁術」という言葉があるが、この贈りものはそれを象徴しているようだ。
- 上杉謙信の塩
-

「雄雌を決するは弓矢なり、塩にあらず。」
「殿、好機にござる。ぜひとも禰知谷(ねちだに)の関に塩留めのご下知を」
にじり寄る諸将を前に、上杉謙信は別の思案に耽っているようにみえた。
永禄11年(1568年)冬、越後・春日山城でのことである。
間者の伝えるところによると、隣国甲斐の覇者・武田信玄は、今川、北条の連合軍により、駿河湾、小田原方面からの魚塩を厳しく差しとめられ、領内は民も兵も大いに苦しんでいるとのこと。
上杉方の諸将は色めき立った。
南からのルートを閉ざされた以上、後は北からの唯一の道を越後領内の禰知谷の関所で押さえれば、いかに信玄とて窮せずにおられまい。
民は疲れ、兵も衰えるであろう。そうしておいて襲いかかるなら・・・。
諸将の脳裡にはこの十数年にわたる武田軍との苦しかった戦いの数々が浮かんでくる。
肉親を、縁者を、友を数え切れぬほど失ってきた。この恨みを
晴らし、雌雄を決するのはこの機をおいて他にない。
「殿、ご決断を」その声をはね返すように、謙信は凛と一声。
「甲斐に使者を!わしが信玄公と争うは弓矢においてなり、塩、糧食にあらず」
大量の塩俵を積んだ荷駄が禰知谷を越え、信玄の居城・松本深志城に入ったのは翌年正月十一日のことであった。
「なに?越後から?」報を受けた信玄は思わず立ち上がった。使者の攻城に曰く、「腹が減っては戦も叶わぬ。
ささやかながら謙信の陣中見舞いでござる。
願わくば民を安んじ兵を養いてのち、再び川中島にて相見えんことを」これを聞いて信玄は天を仰いで呻いたという。
燃えさかる野望のためには父を追い、長男を自刃させたほどのこの戦国の猛将が、なぜかこの後、謙信の背後を衝くような軍馬を一度たりとも向けようとはしなかった。
嫡子・勝頼に「こののちは謙信公を頼れ」と言い残して死んだのはそれから四年後。
 訃報に接した謙信は、食事中の箸を落とし、「ああ、競うべきものすでになし」と涙を流したという。
訃報に接した謙信は、食事中の箸を落とし、「ああ、競うべきものすでになし」と涙を流したという。
川中島に対峙して激闘を重ねた信玄と謙信。
両者の間には、生涯の好敵手として、敵味方を超えた不思議な心の交流が芽生えていたのであろう。
謙信が贈った塩は、その友情の結晶だったのかもしれない。


